SSDのクローンを試して途中で失敗し、起動しない・フォーマットもできず焦っている方は少なくありません。
原因はパーティションやファイルシステムの破損、容量不足、暗号化やドライバー不整合、物理的な不良など多岐にわたり、放置すればデータ消失のリスクが高まります。
この記事では初期チェックからデータ保護、Windows/Linuxでの基本操作、DiskPartやGPartedといったツールの使い分け、さらに安全なフォーマットと復旧・完全消去の選択肢まで実践的に解説します。
初心者でも分かる手順とトラブル別の対処法を揃えているので、読み進めれば自信を持って作業を再開できます。
まずは最初のチェック項目から順に確認していきましょう。
SSDクローン失敗後のフォーマット手順と対策

SSDのクローン作業が失敗した後は、落ち着いて状況を把握することが重要です。
誤った操作でデータを上書きすると取り返しがつかなくなるため、まずは作業を中断してください。
初期チェック項目
まずはケーブル接続と電源供給を確認してください。
別のUSBポートやSATAケーブルで接続をやり直すだけで認識する場合があります。
ディスクがBIOSやUEFIで認識されているかどうかを確認してください。
認識されていない場合は、別のPCで試すか、外付けケースの問題を疑ってください。
また、クローン元とクローン先の容量やパーティション構成を比較して、明らかな不整合がないか確認してください。
データ保護
データ復旧の可能性を残すため、すぐにフォーマットや初期化は行わないでください。
重要なデータが残っている場合は、可能な限りディスクイメージを作成してから作業を進めてください。
書き込みを止めるためにターゲットディスクを読み取り専用モードにする方法もあります。
暗号化が有効なディスクの場合は、解除手順を確認しておきましょう。
バックアップ作成
まずは復旧用のバックアップを作成することを優先してください。
イメージバックアップはファイル単位のコピーよりも復旧に強い手段です。
以下は代表的なバックアップ手順のチェックリストです。
- ディスクイメージの作成
- 重要ファイルの別メディアへのコピー
- チェックサムの生成と保存
- バックアップの検証
Windows基本操作
Windows環境ではディスクの管理ツールからディスクの状態を確認できます。
未割り当て領域の有無やパーティションタイプをここで確認してください。
簡単な初期化やフォーマットはディスクの管理で行えますが、詳細操作はDiskPartの利用を検討してください。
DiskPartを使う際はコマンドの取り扱いに注意して、対象ディスクを誤選択しないようにしてください。
メーカー提供のSSDユーティリティがある場合は、専用ツールでのセキュアイレースが推奨されます。
Linuxではlsblkやfdiskでディスク情報を詳しく確認できます。
パーティションテーブルの修復はgdiskやpartedが便利です。
wipefsで既存のファイルシステムシグネチャを削除し、mkfsで新しいファイルシステムを作成できます。
ddコマンドで全セクタをゼロやランダムで上書きする方法もありますが、SSDには適さない場合があるため注意が必要です。
NVMeドライブではnvme-cliのsecure-erase機能を検討してください。
専用ユーティリティ
市販や無料の専用ユーティリティは、初心者でも安全にフォーマットや消去を行えるメリットがあります。
ツールによってはファームウェア更新や寿命管理機能が含まれている場合もあります。
| ツール | 主な用途 |
|---|---|
| Macrium Reflect | イメージバックアップ |
| Clonezilla | ディスククローン |
| Samsung Magician | ファームウェア更新 |
| CrystalDiskInfo | ディスクヘルス確認 |
安全なフォーマット選択
SSDにはHDDと同じ多重上書き方式は効果が低く、逆に寿命を縮める可能性があります。
メーカー推奨のセキュアイレースやATAコマンドによるSecure Eraseが最も安全で確実です。
Windowsのクイックフォーマットはファイルシステムの再構築に速い反面、データ復旧される可能性があります。
完全消去が必要な場合は、TRIMを適切に発行するか、NVMeの対応コマンドを使用してください。
作業前には必ずバックアップとイメージ保存を行い、手順をメモしてから実行することをおすすめします。
クローン失敗の代表的な原因

SSDクローンが失敗する理由は多岐にわたり、単純な設定ミスから深刻なハードウェア故障まで幅があります。
ここでは実務でよく遭遇する代表的な原因を分かりやすく整理し、原因特定と対処の第一歩をサポートいたします。
クローン中断
クローン処理が途中で止まる原因は、電源断やケーブルの抜けなど物理的な要因が多いです。
ソフトウェアのクラッシュやOSの再起動、ユーザー操作による中断もよく見られます。
一度中断するとパーティション情報が不整合になり、再試行でさらに問題を悪化させることがあるため注意が必要です。
容量不足
ターゲットドライブの空き容量が不足しているとクローンは途中で失敗します。
ソースとターゲットの論理サイズを必ず比較し、余裕を持たせておくことが重要です。
- ターゲット容量がソース未満
- パーティションの縮小未実施
- 未使用領域の誤認識
- クローンツールのサイズ計算の差異
ファイルシステム破損
ファイルシステムが破損しているとクローン作業で読み取りエラーが発生します。
読み取りエラーはクローンソフトを停止させるか、壊れたデータをそのまま複製してしまうリスクがあります。
クローン前にchkdskやfsckで整合性チェックを行うと、成功率が大きく向上します。
パーティションテーブル破損
パーティションテーブルに問題があると、クローン後にターゲットが認識されなくなることがあります。
これはGPTやMBRのヘッダ破損、パーティションの重複などが原因となる場合が多いです。
| 症状 | 原因候補 |
|---|---|
| OSが起動しない | 起動パーティション情報の欠落 |
| ディスクが未初期化と表示 | GPTヘッダ破損またはMBR上書き |
| パーティションサイズが不正 | パーティションテーブルの不整合 |
暗号化設定
BitLockerやファイルシステム暗号化が有効な状態では、クローンは失敗するか、コピー後に復号できなくなることがあります。
暗号化されたパーティションは複製ではなく、事前の解除や復号キーの準備が必要です。
企業環境ではキーマネジメントの確認をしないと大きな障害につながるため、慎重に扱ってください。
ドライバー不整合
クローン先の環境で必要なSATAコントローラやNVMeドライバーが異なると、クローンは成功してもブートできない場合があります。
RAID構成やAHCIとIDEの切替えなど、コントローラ設定の差異がトラブルの種になります。
事前にターゲット環境のドライバーとモードを確認し、必要ならドライバーを組み込んでおくと安心です。
物理不良
SSD自体の物理不良はクローン失敗の最も深刻な原因となります。
SMARTエラーや不良セクタの増加、コントローラの不調は読み書きを妨げ、クローン処理を止めます。
この場合は無理にクローンを続けず、まずはディスクのイメージ取得や専門の復旧サービスに相談することをおすすめします。
フォーマットできない場合の手順別対処

クローン失敗後にフォーマットができない場合は、原因別に手順を分けて対処するのが効率的です。
ここではWindowsとLinuxの標準ツールから、専用の低レベルコマンドやファームウェア操作までを順に説明します。
DiskPart
DiskPartはWindowsに内蔵された強力なコマンドラインツールで、管理者権限で実行する必要があります。
誤操作でデータを消失するリスクが高いため、対象ディスクを間違えないように注意してください。
代表的なコマンドと用途は次の表を参考にしてください。
| コマンド | 用途 |
|---|---|
| list disk | ディスク一覧表示 |
| select disk N | 対象ディスク選択 |
| clean | パーティション情報削除 |
| clean all | 全セクタ上書き消去 |
| convert gpt | GPT変換 |
| create partition primary | パーティション作成 |
cleanコマンドはパーティションテーブルを消去しますが、SSDではTRIMやメーカーのコマンドの方が望ましい場合があります。
clean allは時間がかかり、SSDに対しては寿命を縮める可能性があるため、使用は慎重にしてください。
ディスクの管理
Windowsのディスクの管理はGUIで操作でき、初心者にも扱いやすい利点があります。
ディスクの初期化やパーティションの削除、フォーマットが可能で、エラー発生時の状態確認に便利です。
操作できない場合は対象ボリュームをオフラインにするか、ボリュームの割当を解除してください。
「初期化されていません」と表示されるときは、ディスクを右クリックして初期化を試みると復旧する場合があります。
GParted
GPartedはLinux系のパーティション編集ツールで、ライブUSBから起動して利用するのが一般的です。
ブートしてから操作するため、対象ディスクがマウントされていない状態で安全に作業できます。
- ライブUSBで起動
- 対象ディスクのアンマウント
- パーティションのチェックと修復
- 不要パーティションの削除
- 新規パーティションの作成と適用
適用ボタンを押すまでは変更が確定しない設計なので、操作を最終確認してから実行してください。
wipeコマンド
wipeやshredなどの上書きコマンドはデータの上書き消去に使えますが、SSDでは効果が限定的です。
SSDでは物理的なリマッピングやウェアレベリングの影響で、確実に消去するにはホスト側のTRIMやSecure Eraseを使うのが望ましいです。
Linuxではblkdiscardやnvme formatなど、デバイスに応じた廃棄コマンドが用意されていますので、メーカーの推奨手順を確認してください。
上書き消去は時間と書き込み量を消費しますので、必要性を検討してから実行してください。
セクタ修復ツール
論理障害やファイルシステムの破損が原因でフォーマットできない場合は、専用の修復ツールを使うと復旧できることがあります。
Windowsではchkdsk /fまたはchkdsk /rを試行し、読み取り専用スキャンで問題箇所を特定してください。
Linuxではbadblocksやe2fsckといったツールがあり、読み込み専用のチェックを最初に行うことを推奨します。
物理的不良セクタが見つかった場合は、メーカーの診断ツールでファームウェアによるリマッピングを試みるのが得策です。
ファームウェアリセット
SSDの挙動がおかしいときは、ファームウェアの不具合が原因である場合があります。
メーカーが提供するファームウェア更新ツールやSecure Erase機能でリセットできることがあり、これにより論理状態が正常化する場合があります。
ただしファームウェア更新は失敗するとデバイスが使えなくなるリスクがあるため、必ず指示に従い、電源供給が安定した環境で実行してください。
更新前には必ず重要データのバックアップを作成してから作業してください。
データを残す復旧と完全消去の選択肢

SSDのクローン失敗後にまず考えるのは、データを残すか完全に消去するかの方針決めです。
目的により使う手法が大きく変わるため、後戻りできない操作を行う前に選択肢を整理しておくことが重要です。
ファイル復旧ソフト
まずはファイル復旧ソフトを使って論理レベルでの復旧を試みる方法があります。
市販やフリーのツールはクイックスキャンとディープスキャンを備えており、削除やパーティション損傷からの復元に期待できます。
作業時は復旧対象のSSDに直接書き込みを行わないように別媒体へ復元することを徹底してください。
成功率は障害の種類と進行度合いで変わり、浅い障害ほど短時間で復旧できる傾向があります。
イメージバックアップ
物理的な操作や高度な復旧を行う前にディスク全体のイメージを取得しておくと安全です。
イメージを保存しておけば、誤った操作で状況が悪化しても復元元が手元に残ります。
ツールはdd系や専用のクローンソフトを利用でき、圧縮や検証オプションを使うことで効率的に保存できます。
イメージ取得は時間がかかる場合がありますので、作業時間と保存先容量を事前に確保してください。
論理復旧サービス
自力での復旧が難しい場合は専門の論理復旧サービスに相談する方法が有効です。
サービスではソフトウェアでの復旧やファイルシステムの修復を安全に実施してもらえます。
費用と納期は障害の程度で変わるため、見積もりを取ってから依頼するのが賢明です。
- 対応範囲が広い
- 診断で原因特定
- 高難度の復旧が可能
- 費用が発生
上書き消去ソフト
データを残さず完全消去する場合は上書き消去ソフトを利用します。
上書き回数や方式によって消去の強度が変わり、用途に合わせて選ぶべきです。
消去前には復旧が不可能になる点を十分に理解のうえで実行してください。
| 方式 | 用途例 |
|---|---|
| ゼロフィル | 一般的な完全消去 |
| ランダム上書き | より高い安全性を要求する場面 |
| 複数回上書き | 極めて高い再生防止が必要な場合 |
物理破壊
最終手段として物理破壊を選ぶと、データの復元可能性をほぼゼロにできます。
シュレッダーでの裁断やドリルでの貫通など、確実な方法を選択してください。
廃棄や破壊の際は環境規制や企業ポリシーに従い、安全に処理することが求められます。
また、重要データが含まれる場合は破壊後に確認手順を設けると安心です。
クローン成功率を上げる事前準備と予防策
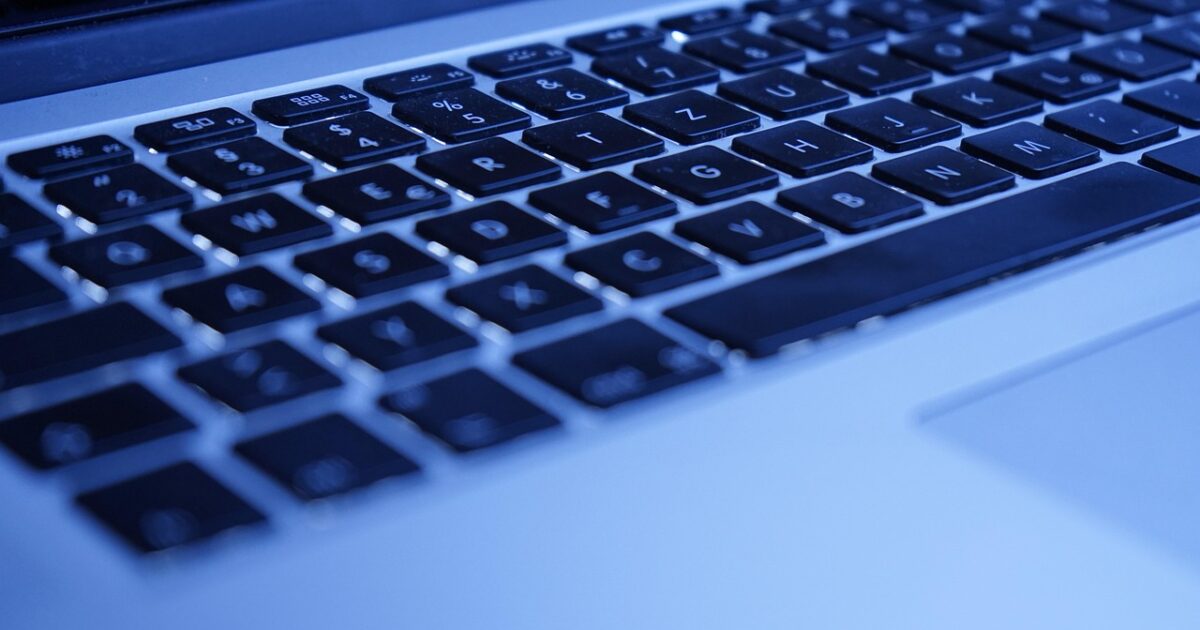
SSDのクローン作業は準備で結果が大きく変わります。
ここでは失敗を減らすための具体的な手順と注意点をわかりやすく解説します。
バックアップの作成
最優先の対策は必ずバックアップを取ることです。
クローン作業中にデータが失われても復旧できるように、複数の手段を用意してください。
- ディスクイメージを作成
- 重要ファイルの個別コピー
- クラウドへのアップロード
- 設定のエクスポート
イメージを取る場合は、作成したファイルが破損していないかを検証する習慣をつけてください。
ディスクヘルスチェック
クローン前にSSDの健康状態を確認することは非常に重要です。
SMART情報の確認で寿命や代替セクター数を把握し、異常があれば作業を中止する判断をしてください。
WindowsならCrystalDiskInfo、Linuxならsmartctlなどを使い、読み書きエラーの傾向をチェックしてください。
容量とパーティション調整
ターゲットSSDの容量はソースの使用容量以上を確保する必要があります。
余裕を持たせると同時にパーティション境界を整えておくと、クローン後のブート問題を減らせます。
パーティションのアライメントやファイルシステムの不整合を事前に修正しておくことをおすすめします。
暗号化解除
ソースまたはターゲットに暗号化がかかっている場合、作業前に解除しておく方が安全です。
BitLockerやFileVault、LUKSなどはクローン時に互換性トラブルを起こしやすいので、可能なら復号を行ってください。
復号が難しいケースでは、暗号化対応のクローンツールを使うか、専門家に相談するのが無難です。
最新ドライバーとファームウェア
SSDやマザーボードのファームウェア、OSのストレージドライバーは最新版にしておくとトラブル発生率が下がります。
メーカーの公式サイトからアップデートを入手し、手順に従って適用してください。
| 項目 | 対策 |
|---|---|
| SSDファームウェア コントローラ改善 |
メーカー公式ツール使用 手順に従う |
| ストレージドライバー AHCI NVMeドライバー |
OS互換の最新版導入 再起動で反映 |
| BIOS UEFI | ストレージ設定確認 最新BIOS適用 |
ただしファームウェア更新はリスクも伴うため、事前にバックアップを確実に行ってください。
信頼できる接続ケーブル
接続性の不安定さはクローン失敗の意外な原因になります。
SATA接続が可能なら直接接続で作業する方が安定しますし、USBアダプタを使う場合は高品質のチップ搭載製品を選んでください。
ケーブルや外付けケースの電源が不足すると転送エラーが生じますので、セルフパワーの機器を使うなど電源供給にも注意してください。
作業前の最終確認

作業を始める前に、対象のSSDが正しく認識されているか、接続ケーブルや電源に緩みがないかを必ず確認してください。
バックアップは必須です。
重要なデータが別媒体やクラウドに保存済みかを再確認します。
使用するOSで管理者権限があるか、クローン・フォーマット用ソフトの最新版とドライバーやファームウェアの互換性が整っているかをチェックしてください。
不審な音や異常な温度、物理的な損傷が見られる場合は無理に作業を続けず、専門業者に相談することをおすすめします。

