新しいSSDに乗り換えたいけれど、どのソフトを選べば安全に移行できるか不安に感じていませんか。
クローン方式や対応OS、容量差、起動設定などを誤ると起動しない・データが消える可能性があり、選択は重要です。
この記事では初心者にも分かりやすく、信頼性や使いやすさを基準におすすめのSSDクローン用ソフトを厳選して比較します。
EaseUS Todo BackupやMacrium Reflect、Clonezilla、Samsung Data Migrationなど主要製品を用途別に解説し、導入前の確認項目や実践手順、トラブル対処も丁寧に扱います。
まずは各ソフトの特徴と選び方のポイントを確認して、あなたの環境に最適な一手を見つけましょう。
SSDクローンソフトのおすすめ一覧

ここでは用途やレベル別におすすめできるSSDクローンソフトを紹介します。
操作性や対応OS、無料版の有無など、実際に使う場面を想定して解説します。
EaseUS Todo Backup
使いやすさを重視した定番ツールで、初心者にも扱いやすいインターフェースが魅力です。
クローン機能のほか、イメージバックアップや復元機能も充実しています。
- 無料版あり
- 初心者向け
- ディスククローン
- イメージバックアップ
Macrium Reflect
信頼性が高く、業務用でもよく使われるソフトウェアです。
イメージベースのバックアップと差分バックアップに強みがあり、復元の自由度が高いです。
AOMEI Backupper
多機能でコストパフォーマンスに優れる点が魅力です。
ディスクやパーティションのクローンに加え、スケジュールバックアップや同期機能も備えています。
Clonezilla
オープンソースで無料、軽量かつ高速なクローンが可能です。
GUIが簡素なため慣れが必要ですが、柔軟な運用ができます。
Samsung Data Migration
Samsung製SSDのクローン作成に特化した公式ツールです。
インストール後はほとんどの作業が自動化されており、手早く移行できます。
MiniTool Partition Wizard
パーティション管理機能とクローン機能が両立している便利なユーティリティです。
ディスクのリサイズや整列など、クローン後の最適化にも対応しています。
| 機能 | 特徴 |
|---|---|
| パーティション管理 | 無料版あり |
| クローン機能 | 初心者向け |
| 最適化ツール | Windows対応 |
Acronis True Image
総合的なバックアップとセキュリティ機能を備えた有償ソフトです。
ランサムウェア対策やクラウド連携が強化されており、企業利用にも耐えます。
4DDiG Partition Manager
比較的新しいツールですが、分かりやすいUIで初心者にも扱いやすい設計です。
パーティションの復旧やフォーマット、クローン作成まで一通りカバーしています。
導入前の確認項目

SSDへクローンを作成する前には、いくつかの確認項目を順番にチェックしておくと安全です。
小さな見落としが後で大きな手間になることがあるため、手順を整理して進めてください。
ディスク容量の確認
まずはソースディスクの使用容量を正確に把握してください。
ターゲットとなるSSDの容量がソースより小さい場合は、不要ファイルの削除やパーティションの縮小が必要になります。
- 使用中データの合計
- システム領域のサイズ
- 将来の余裕を考えた予備容量
MBR/GPTの確認
ブート方式やパーティション形式がMBRかGPTかで、クローン後の起動可否が変わることがあります。
Windowsではディスクの管理やdiskpartコマンド、macOSやLinuxではdiskutilやgdiskなどで確認できます。
UEFIブートを使っている場合はGPTを推奨しますので、必要に応じて変換を検討してください。
変換する際はデータ消失のリスクがあるため、バックアップを確実に取ってから進めることをおすすめします。
接続方式の確認
ターゲットSSDをどのように接続するかで、クローンの方法や速度が変わります。
外付けケースや変換アダプタを使う場合は電源やケーブルの規格も確認してください。
| 接続方式 | 代表例 |
|---|---|
| SATA | 内蔵SATAドライブ 2.5インチSSD |
| NVMe | M.2スロット接続 PCIe接続の高速SSD |
| USB | 外付けケース経由 USB3.0やUSB-CポータブルSSD |
バックアップ作成
クローン作業の前には必ずバックアップを取得してください。
システムイメージを作成して外付けドライブやクラウドに保存しておくと安心です。
バックアップは一度だけでなく、復元テストを行って確実に使えることを確認しましょう。
複数世代のバックアップを残しておくと、想定外のトラブルにも対応しやすくなります。
選び方の具体基準
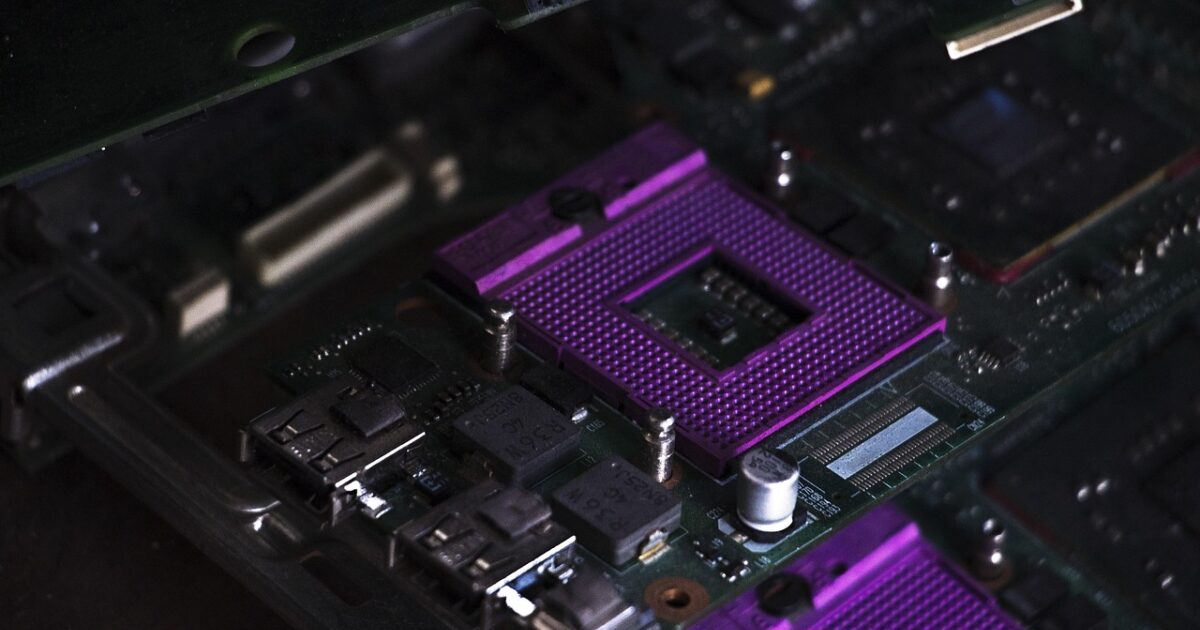
SSDクローンソフトを選ぶ際の判断基準を具体的に整理して説明します。
性能面だけでなく、互換性や運用のしやすさも重要です。
対応OS
まず対応OSを確認してください。
Windowsのみ対応のソフトもあれば、MacやLinuxに対応する製品もあります。
UEFIやBIOS環境でのブートに依存する場合がありますので、使用している環境に合わせて選ぶ必要があります。
さらに32bit/64bitの違いや、サーバー用途での対応の有無もチェックしたほうが良いです。
クローン方式
クローンの方式によって使い勝手や成功率が変わります。
用途に合った方式を理解しておくと、失敗や手戻りを減らせます。
- ディスク全体クローン
- パーティション単位クローン
- ファイルベースコピー
- 増分クローン
- セクター単位クローン
システム丸ごと移行したい場合はディスク全体クローンが便利です。
容量差がある場合や特定パーティションだけ移したいときはパーティション単位やファイルコピーが適します。
SSD最適化機能
TRIMコマンドの実行やパーティションアライメントの調整は重要な機能です。
これらが適切に働かないと、移行後にSSDの性能低下や寿命短縮を招くことがあります。
オーバープロビジョニングの設定や古いデータの最適化を自動で行う機能があるかも確認してください。
暗号化対応
暗号化されたドライブを扱う場合、クローンソフトの対応状況を必ず確認してください。
BitLockerやFileVaultなどのボリューム暗号に対して、復号した上でクローンするのか、そのままコピーできるのかはソフトにより異なります。
TCG Opalなどのハードウェア暗号化に対応しているかどうかも、業務用途では重要な判断材料です。
クローン前に復号やキー管理の準備を行うことを推奨します。
速度と性能
クローンの速度は使用するアルゴリズムや圧縮の有無、マルチスレッド対応で変化します。
短時間で終わらせたい場合は圧縮や並列処理の有無をチェックしてください。
下の表は性能評価で注目すべき項目を整理したものです。
| 評価項目 | 重視ポイント |
|---|---|
| シーケンシャル速度 | 大容量コピーの速度 |
| ランダムIOPS | 小ファイルの処理性能 |
| 圧縮対応 | 転送データ量の削減 |
| マルチスレッド処理 | 複数コア活用 |
| SSD最適化機能 | TRIMやアライメント |
ライセンスと価格
無料版と有料版で機能差が大きい製品が多くあります。
個人利用なら無料版で十分な場合もありますが、業務用途ではサポートや追加機能を含む有料版が安心です。
サブスクリプション型と永続ライセンス型では長期コストが変わりますので、更新やサポート体制も含めて比較してください。
複数台導入する場合はボリュームライセンスや企業向けプランの有無を確認し、総コストと利便性のバランスで判断することをおすすめします。
クローン作成の手順

SSDのクローン作成は手順を守れば安全に実行できます。
ここでは準備から動作確認まで、実際の作業で迷わないように順を追って解説します。
準備
まずは必要な機材とソフトを揃えておくことが重要です。
電源やケーブルの確認を怠ると途中で中断してしまう恐れがありますから、事前に点検してください。
- 外付けケースまたは変換アダプタ
- クローンソフト
- 十分な電源供給
- バックアップ媒体
- 接続ケーブルの予備
また、クローン先のSSDは初期化や不要パーティションの削除を済ませておくと作業がスムーズです。
ソースディスクの選択
ソースディスクはシステムが入っているディスクを正確に選んでください。
誤ってデータディスクを選ぶと意図した環境が複製できませんので、ディスク名や容量を確認して判別してください。
また、不要な大容量ファイルや一時ファイルを削除しておくと、クローン先の容量に余裕が生まれます。
ターゲットディスクの選択
ターゲットSSDの容量はソースの使用領域を上回る必要があります。
MBRとGPTの整合もここで確認しておくと起動トラブルを減らせます。
余裕があればファームウェアやドライブのファイルシステムを最新にしておくと相性問題が起こりにくくなります。
クローン実行
クローン実行時はソフトの指示に従い、ソースとターゲットの選択を慎重に行ってください。
処理中はケーブルを触らない、電源を切らないなど基本ルールを守って安定させることが肝心です。
| クローン方式 | 用途 |
|---|---|
| セクタ単位コピー | 完全複製 |
| ファイル単位コピー | 不要領域除外 |
| 高速クローン | 最短時間 |
状況に合わせて上記の方式を選び、必要があればパーティションサイズの調整を行ってください。
クローン処理には時間がかかる場合がありますから、完了まで放置できる環境を用意しておくと安心です。
動作確認
クローンが終わったらターゲットSSDから正常に起動するかを確認します。
BIOSまたはUEFIの起動順序を変更して、クローン先を最優先に設定してください。
起動後はデバイスマネージャやディスク管理でドライブが正しく認識されているかをチェックしてください。
必要に応じてOSのアクティベーションやドライバ更新も行い、不具合がないか実際にアプリを起動して動作確認してください。
トラブル対処と解決策

SSDクローン作業で発生しがちなトラブルと、その具体的な解決手順をまとめます。
事前に原因を切り分けることで、余計な時間を減らし、復旧の成功率を高めることができます。
クローン失敗
クローンが途中で失敗する原因は多岐にわたります、代表的な要因を把握することが重要です。
- ディスク容量不足
- 不良セクタの存在
- 接続不良やケーブル不具合
- クローンソフトのバグやバージョン不整合
- 電源供給の問題
まずはログやエラーメッセージを確認してください、ログには原因特定のヒントが残っていることが多いです。
不良セクタが疑われる場合は、ディスク検査ツールで表面スキャンを行い、可能ならば不良領域を隔離することをおすすめします。
接続に問題がありそうなら、SATAやUSBケーブルの交換、別ポートでの接続を試してください。
クローンソフトのバージョンが古ければ最新にアップデートし、同じ手順で再試行してください。
それでも失敗する場合は、セクター単位のクローンとファイル単位のバックアップを比較し、別の方式で復旧を図るとよいです。
クローン後にPCが起動しない場合は、ブート情報やパーティションの状態を確認します。
よくある原因は、MBRとGPTの不一致、ブートローダーの破損、EFIパーティションの欠落です。
Windowsの場合は回復ドライブから起動し、bootrecやbcdbootコマンドでブート情報を修復してください。
UEFI設定で起動順やセキュアブートの設定を見直すことも重要です、特にNVMe SSDを換装した場合は設定変更が必要になることがあります。
ディスクをアクティブにする必要があるケースでは、diskpartで対象ディスクのアクティブ化を行ってください。
それでも起動しないときは、元のディスクとターゲットを入れ替えて問題の切り分けを行うと原因追及が進みます。
容量差の問題
ソースディスクより小さいSSDへクローンしようとすると、容量不足で失敗することがあります。
この場合はパーティションを縮小し、使用済み領域がターゲットより小さくなるよう調整してください。
クローンソフトに「インテリジェントクローン」機能があれば、自動で縮小してくれることがあります、うまく動作しない時は手動でパーティションを操作します。
不要ファイルの削除や大容量データの外部移動を行い、総使用容量を減らすことも有効です。
ファイルシステムの違いが影響する場合もあるため、NTFSやexFATなど対象に応じた確認を忘れずに行ってください。
パーティション不整合
クローン後にパーティションの順序やサイズが不適切になるケースがあります。
特にシステム予約領域やEFIパーティションが正しく複製されていないと、起動や更新時に問題が発生します。
クローン前に重要な隠しパーティションを確認し、ソフトのオプションでそれらを含めてクローンする設定にしてください。
必要に応じてパーティション編集ツールで境界の再配置やアライメント調整を行い、最適化を図るとよいです。
MBRからGPTへの変換が必要な場合は、データのバックアップを取り、適切な手順で変換してください。
ドライバと互換性
新しいSSDへ換装した際、ドライバやファームウェアの不整合で不具合が出ることがあります。
| 問題 | 対策 |
|---|---|
| NVMeドライバ未導入 | メーカーサイトからドライバの入手 |
| 古いファームウェア | SSDのファームウェア更新 |
| BIOS設定不一致 | AHCIとNVMeの設定確認 |
まずはメーカー提供の最新ドライバとファームウェアを適用してください、特にNVMe SSDは専用ドライバが必要な場合があります。
BIOSやUEFIの設定でモードがIDEやRAIDになっていると起動問題が発生することがあるため、AHCIやNVMeモードを確認してください。
古いOSは新しいSSDに対応していない場合があるため、OS側の更新やチップセットドライバの導入も検討してください。
さらに、他社製ツールでクローンした後はドライバの再インストールやデバイスマネージャでの再認識を行うと安定しやすくなります。
導入後の運用指針

SSD導入後は、まずSMART監視やメーカー提供のツールで状態を定期確認します。
TRIMや最適化設定を有効にし、ファームウェアは定期的に更新してください。
容量は常に余裕を持たせ、空き領域を10〜20%程度確保すると性能低下を防げます。
不要なデフラグは避けてください。
バックアップとブート用のリカバリメディアは別媒体に保存し、定期的に復元テストを行う習慣にしてください。
長期運用ではログの記録やシリアル、保証情報の管理を行い、トラブル発生時に迅速に対応できるよう備えておくと安心です。

