PCの起動が遅く、換装で失敗したくないと不安に感じていませんか。
SSDクローンは手順を誤るとデータ消失やブート不能を招くため、初めてだと特にハードルが高く感じられます。
この記事ではEaseUSを使ったSSDクローンの準備から換装後の最適化、トラブル対応までをわかりやすく解説します。
準備機器やバックアップ、容量差がある場合のパーティション調整、M.2やSATAの接続注意点、Windows側の前処理、クローン後の確認項目を網羅します。
実作業に入る前のチェックリストも用意しているので、手順どおり進めれば安全に移行できます。
続きで具体的な手順を確認しましょう。
EaseUS SSDクローン実践ガイド
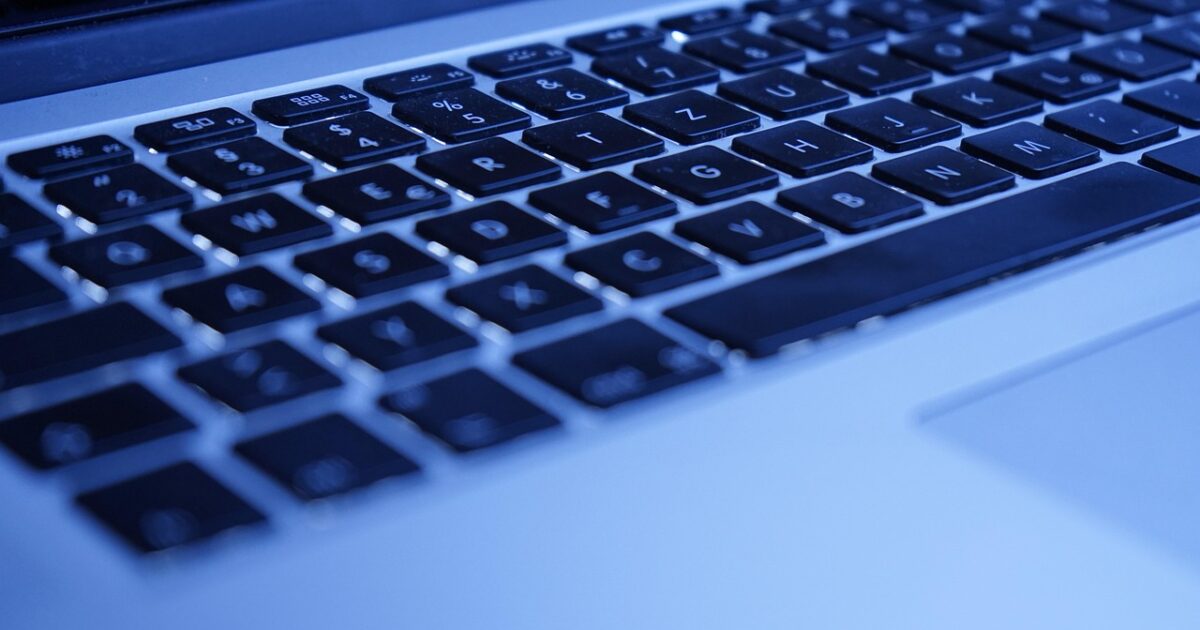
この章では、EaseUS Todo Backupを使って安全にSSDをクローンする手順を丁寧に説明します。
初めての方でも迷わないように準備からトラブル対応まで網羅します。
準備機器
まず必要な機器を揃えてください。
| 機器 | 用途 |
|---|---|
| 元のSSD | ソースディスク |
| 移行先のSSD | ターゲットディスク |
| SATAまたはUSBケーブル | 接続用 |
| 外付けケースまたはアダプタ | 一時接続用 |
| ドライバー類 | 換装作業用 |
機器は新品でなくても構いませんが、接続ケーブルの状態は確かめてください。
移行先SSDの空き容量が足りるかを事前に確認しておくと後の手間が減ります。
データバックアップ
クローン作業の前に重要データを必ずバックアップしてください。
ファイル単位のバックアップと、システムイメージの両方を用意すると安心です。
クラウド保存や外付けHDDへのコピーなど、複数の保存先を使うことをおすすめします。
バックアップ後はファイルが正しく保存されているか、ランダムに開いて確認してください。
SSD接続方法
接続方法は環境により複数ありますが、いずれも電源とコネクタの向きに注意してください。
- 内蔵SATA接続
- USB外付けケース
- M.2スロット直挿し
- M.2 to USBアダプタ
ラップトップで内蔵スロットが一つしかない場合は外付けケースを使ってクローンを作成します。
NVMeドライブを外付けで使用する際は、対応するケースとUSBの規格に注意してください。
クローン設定項目
EaseUSのクローン画面では、ソースとターゲットの選択が最初の要点です。
「ディスククローン」と「システムクローン」の違いを理解して適切な方を選んでください。
パーティションのサイズ調整やアライメントのオプションがあり、SSD最適化はチェックしておくと良いです。
容量差がある場合はターゲット側のパーティションを手動で調整するか、自動調整に任せる方法があります。
クローン作業の実行
ソースとターゲットを正しく選んだら、変更のプレビューで差分を確認します。
プレビューで問題がなければ、クローン実行を開始してください。
作業中は電源を切らないようにし、ノートPCなら電源アダプタを接続しておきましょう。
完了までの時間は容量や接続方式で変わりますが、目安時間より長くなることがある点に留意してください。
換装と起動確認
クローン完了後はPCの電源を切り、元のドライブと入れ替えを行います。
換装後はBIOSまたはUEFIで起動ディスクの優先順位を新しいSSDに設定してください。
初回起動でWindowsが正常に立ち上がるか確認し、必要ならスタートアップ修復を実行します。
ドライブレターやユーザープロファイルの整合性も素早くチェックしてください。
クローントラブル対応
起動しない場合はUEFIとレガシーの設定を見直すことが有効です。
ディスクシグネチャの衝突やブートローダの不整合が原因のこともあります。
その場合はWindowsの修復ツールやEaseUSの復旧ツールを使って復旧を試みてください。
クローンに失敗する頻度が高いときは、別のケーブルや外付けケースで再試行すると成功率が上がります。
最終手段として、重要データのバックアップからクリーンインストールを行う方法も考えてください。
容量が異なるSSDへのクローン手順

容量が異なるSSDにクローンするときは、単に接続して実行するだけでは問題が発生することがあります。
ここでは容量差の確認から最適化オプションまで、実務で役立つ手順を分かりやすく解説します。
容量差の確認
まずは元ディスクの使用済み容量とクローン先SSDの総容量を正確に確認してください。
Windowsのディスク管理やEaseUS内のディスク情報で使用領域をチェックすることをおすすめします。
使用済み容量がクローン先より大きい場合は、不要ファイルの削除やパーティション縮小が必要になります。
パーティション縮小
容量の小さいSSDへクローンする場合は、クローン元のパーティションを先に縮小しておきます。
EaseUSのパーティション管理機能を使えば、システムパーティションを安全に縮小できます。
縮小作業の基本手順は次の通りです。
- 不要ファイルの削除
- ディスクのデフラグ(SSDでは不要だがHDD併用時に有効)
- パーティション縮小の実行
- 縮小後の領域確認
縮小では、システムのスナップショットやバックアップを先に取っておくと安全です。
セクタバイセクタ設定
クローン作業には通常コピーとセクタバイセクタコピーの選択肢があります。
セクタバイセクタコピーはディスクの全セクタを丸ごと複製するため、データの完全一致が必要な場面で有効です。
ただし、クローン先が元より小さい場合や空き領域を省きたい場合は使用できないことがあります。
下表で両者の特徴を簡潔に比較します。
| 設定名 | 特徴 |
|---|---|
| セクタバイセクタコピー | 完全複製 |
| インテリジェントコピー | 空き領域を省く |
| 注意点 | 容量制約あり |
状況に応じてどちらを選ぶべきか判断してください。
SSD最適化オプション
クローン画面にあるSSD最適化オプションは必ず確認してください。
主な項目として4KアライメントやTRIM有効化、SSD向けの最適化設定があります。
4Kアライメントを有効にすると書き込み性能が向上し、寿命にも良い影響があります。
また、クローン後にパーティションを最大化して余った領域を有効活用するオプションも便利です。
クローン実行前にこれらの設定を有効にし、完了後はTRIMが有効かを確認してください。
M.2/NVMeとSATAの接続と注意点

M.2やNVMeのSSDは形状や接続方式が多様で、SATA SSDとは技術的に大きく異なります。
ここではコネクタの互換性、外付けケースの使い方、そしてBIOSやUEFIでの注意点をわかりやすく解説いたします。
コネクタ互換性
M.2スロットにはキー配列があり、主にMキーとBキーが存在します。
NVMeはPCIeレーンを使用するため、Mキーのスロットで動作することが多いです。
一方でM.2 SATAはソケットは同じでも、内部的にはSATA信号を使うため、NVMeスロットで動作しない場合があります。
フォームファクタの違いにも注意が必要で、2242や2260、2280など長さのバリエーションがあります。
物理的に合っても、ピン配置やキーが一致しないと装着できませんので、必ず仕様を確認してください。
PCIeアダプタやM.2→SATA変換アダプタを使う方法もありますが、速度や互換性の制約が出ることがあります。
発熱も見落としがちなポイントで、NVMeは高性能ゆえに放熱対策が必要になることが多いです。
外付けケース利用
ノートPCやデスクトップで内部に余裕がない場合、外付けケースを使ってクローンを作成する方法が便利です。
ただし外付けケース経由では接続インターフェースがボトルネックになることが多く、期待する速度が出ない場合があります。
特にUSB接続の種類やケーブル品質によって、NVMeの性能が十分に発揮されない点に注意してください。
外付けケースを選ぶ際のポイントを箇条書きでまとめます
- 対応インターフェース USB3.1Gen2 USB3.2 TypeC
- 対応ドライブ NVMe専用 M.2SATA対応
- UASP対応の有無
- 放熱設計 ヒートシンク搭載
- 電源供給 バスパワー対応か外部電源か
クローン作業時は安定した接続を確保するため、直接マザーボードに接続できる場合は内部接続を優先することをおすすめします。
BIOS/UEFI設定
クローン後に新しいSSDから確実に起動するため、BIOSまたはUEFIの設定確認が不可欠です。
ブートモードがLegacyになっていると、UEFI専用のNVMeブートが行えないことがありますので、モードを確認してください。
またセキュアブートやCSMの設定により、クローン後の起動に影響を与える場合があります。
代表的な設定と推奨値を表で示します
| 設定項目 | 推奨値 |
|---|---|
| ブートモード | UEFI |
| セキュアブート | 一時的無効 |
| SATAモード | AHCI |
| CSM | 無効 |
| NVMeサポート | 有効 |
設定変更後は保存して再起動し、ブート順が新しいSSDを優先するようにしてください。
BIOSのバージョンが古いとNVMe対応が不十分な場合がありますので、必要に応じてファームウェアの更新を行ってください。
クローン前のWindows環境準備

クローン作業を始める前に、Windows側の環境を整えておくと失敗や手戻りを減らせます。
特に暗号化やディスクの不具合、不要ファイルや古いドライバはクローン中や起動後のトラブル原因になります。
ここではBitLockerの扱い、ディスク状態の確認、不要ファイルの掃除、ドライバ更新について実務的に解説します。
BitLocker解除
まずはBitLockerが有効かどうかを確認してください。
管理者としてコマンドプロンプトを開き、manage-bde -status C: を実行すると暗号化状態が確認できます。
暗号化されている場合は、必ず回復キーをバックアップしてから解除または一時停止してください。
解除はコントロールパネルのBitLocker管理画面から行う方法と、manage-bde -off C: を使うコマンド操作の方法があります。
解除には時間がかかることがあり、ノートPCなら電源に接続したまま実行するようにしてください。
デバイス暗号化が有効な軽量機では、設定アプリのデバイス暗号化項目から操作する必要があります。
ディスク状態の確認
クローン元のディスクに不良セクタやファイルシステムの不整合があると、クローン後に問題が発生しがちです。
まずはS.M.A.R.T.情報とファイル整合性のチェックを済ませておきましょう。
| 確認項目 | 推奨ツール |
|---|---|
| S.M.A.R.T情報 | CrystalDiskInfo |
| 表面エラー | chkdsk |
| ファイル整合性 | sfc scannow |
| パーティション情報 | ディスクの管理 |
Cドライブの整合性は管理者権限でchkdsk /f を実行して確認してください。
システムファイルの検査はsfc /scannowで行い、必要ならDISMでイメージ修復を行います。
またディスクがダイナミックや暗号化など特殊構成になっていないかをディスクの管理でチェックしてください。
不要ファイルの削除
クローン先の容量が小さい場合は、事前に不要データを整理しておくと移行がスムーズになります。
特に一時ファイルや大きなダウンロードフォルダは優先して整理することをおすすめします。
- 一時ファイルの削除
- ダウンロードフォルダの整理
- ごみ箱の空にする
- 休止ファイルの無効化
- システムの復元ポイントの整理
休止ファイルはpowercfg -h off で無効化すると大きな容量を確保できます。
ページファイルを一時的に別ドライブへ移すかサイズを下げる方法も有効です。
SSDに対しては通常のデフラグは不要ですので、Windowsの最適化を使ってTRIMのみ実行してください。
ドライバ更新
ストレージコントローラやNVMeドライバが古いと、クローン後の起動や性能に影響することがあります。
まずはWindows Updateで配布される基本ドライバを取り込み、そのうえでマザーボードやSSDメーカーの最新ドライバを導入してください。
Intel RSTやAMDのチップセットドライバ、各ベンダーのNVMe専用ドライバは特に重要です。
BIOSやUEFIのバージョンが古い場合は、リスクと手順を確認したうえでアップデートを検討してください。
更新後は必ず再起動して、ドライバ適用が正しく行われたことを確認してください。
クローン後の最適化と確認項目

クローン作業が完了したら、単に起動するだけで終わりにしないことが重要です。
性能と安定性を確保するための基本チェックを順に行ってください。
TRIM有効化
TRIMはSSDの寿命と性能維持に欠かせない機能です。
Windowsではコマンドプロンプトを管理者権限で開き、fsutil behavior query DisableDeleteNotifyで状態を確認できます。
返り値がDisableDeleteNotify = 0ならTRIMは有効、1なら無効です。
無効の場合はfsutil behavior set DisableDeleteNotify 0で有効化してください。
NVMeや一部ベンダー固有のドライバでは、メーカー公式ツールで最適化設定が必要な場合がありますので確認しましょう。
Linux環境ならfstrimコマンドやsystemctl enable fstrim.timerで定期実行を設定すると便利です。
ブート順確認
新しいSSDから正しく起動するかどうかは最優先で確認してください。
PCを再起動してBIOSまたはUEFI設定画面に入り、ブートオーダーで新SSDまたはWindows Boot Managerが最優先になっているか確認します。
旧ドライブが接続されたままだとブート優先度やブートローダーの競合で別のディスクから起動することがありますので、必要に応じて一時的に外してください。
UEFIとレガシー(CSM)の設定がクローン元と異なると起動しないことがありますので、モードの一致を確認することをおすすめします。
セキュアブートを利用している場合は、新SSDで問題が出るなら一時的に無効化して試すと原因切り分けがしやすいです。
ディスク容量確認
クローン直後はパーティションサイズや未割り当て領域の確認が必要です。
ディスク管理ツールでパーティション構成を確認し、Cドライブなど主要パーティションが期待通りのサイズになっているか見てください。
- システムパーティションのサイズ
- 未割り当て領域の有無
- Cドライブの拡張可否
- 回復パーティションの位置
容量が小さいSSDから大きいSSDに移した場合は、未割り当て領域を既存パーティションに結合して容量を有効活用しましょう。
Windowsのディスク管理で拡張できないときは、EaseUS Partition Masterなどのツールでパーティション移動や結合を行うと簡単です。
パフォーマンス計測
換装後は実測で速度を確認して、メーカー公称値と大きく乖離していないかチェックしてください。
代表的なベンチマークツールはCrystalDiskMark、AS SSD、ATTOなどで、複数のツールで比較すると信頼性が上がります。
テストはシーケンシャルとランダムの両方を計測し、複数回実行して安定した値を採用しましょう。
| テスト項目 | SATA目安 | NVMe目安 |
|---|---|---|
| シーケンシャルリード | 概ね500MB/s以上 | 数千MB/s |
| シーケンシャルライト | 概ね450MB/s以上 | 数千MB/s |
| 4Kランダムリード | 良好な数値が望ましい | 高いIOPSが期待できる |
もしベンチ結果が著しく低い場合は、AHCIモードやNVMeドライバが正しく入っているか、ドライバ更新やチップセットの設定を見直してください。
また、TRIMやディスクアライメントの問題が性能低下を招くことがあるため、先に紹介した確認も合わせて行うと良いです。
移行後のチェックリスト

移行が完了した後に確認すべき項目を、実用的なチェックリストで整理します。
まずは起動とログインが正常か、ブート順やUEFI設定を含めて確認してください。
次にディスク容量やパーティションの状態、OS側で正しく認識されているかをチェックします。
ドライバやソフトの動作を確認し、デバイスマネージャーでエラーが出ていないかも見ておきましょう。
TRIMの有効化やベンチマークで性能を確認し、必要に応じて最適化を行います。
最後にバックアップ設定の更新や、古いドライブのデータ消去と安全な保管/廃棄を忘れず対応してください。
- 起動確認
- ディスク容量とパーティション確認
- デバイスドライバチェック
- TRIM有効化と性能測定
- バックアップ設定の更新
- 古いSSDのデータ消去と処分
