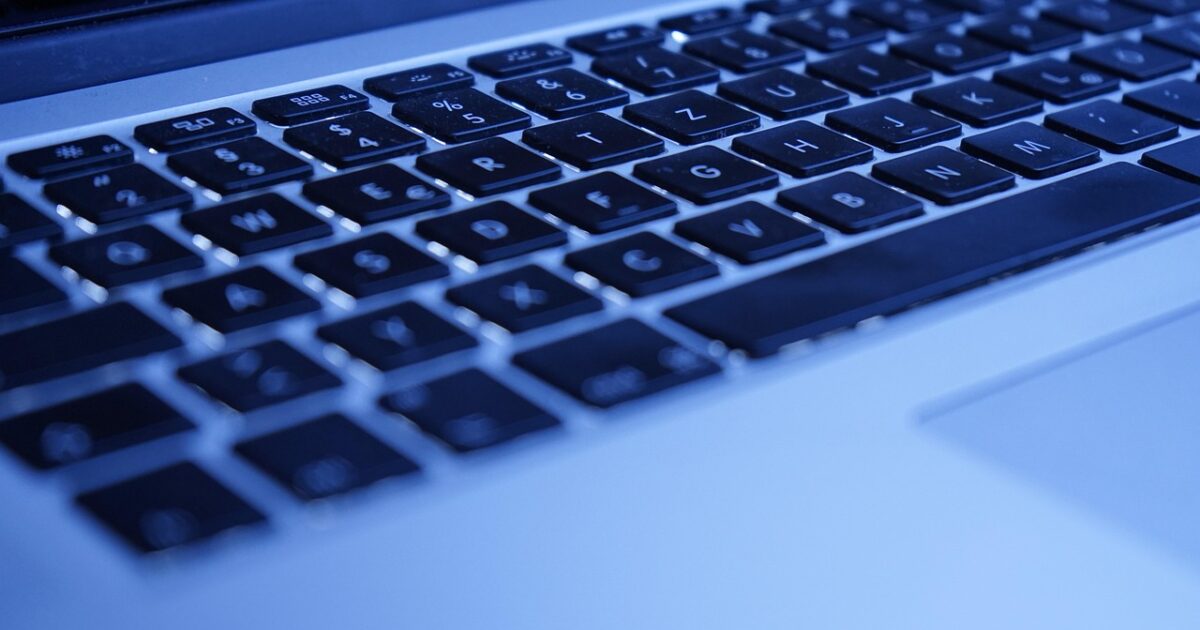OSが入ったSSDを初期化する際、データ消失や起動不能への不安で足踏みしていませんか。
特にWindows11環境ではバックアップ、ライセンス確認、UEFI設定、パーティション選択など注意点が多く、手順を間違えると復旧が難しくなります。
この記事では必要な準備とUSB起動やDiskPartを使った完全消去、別PCでの作業方法まで、実践的な手順をわかりやすく解説します。
さらに再インストール後に必要なドライバ導入やTRIM有効化、最終チェックリストも紹介するので安心して作業できます。
まずはバックアップとライセンス確認の基本から始める手順を続きで確認しましょう。
Windows11でOS入りSSDを初期化する手順

ここではWindows11がインストールされたSSDを安全に初期化するための準備から、消去レベルの選び方までを分かりやすく解説します。
初期化はデータが消える作業ですから、手順を飛ばさずに確認しながら進めてください。
バックアップ
まず最初に、重要なデータのバックアップを確実に行ってください。
システムイメージを取るか、必要なファイルを別のドライブやクラウドにコピーすることをおすすめします。
- ドキュメントフォルダ
- 写真と動画
- メールのバックアップ
- ブラウザのブックマーク
- アプリの設定ファイル
バックアップ後は、データが正しく復元できるか簡単に確認しておくと安心です。
ライセンス確認
Windowsのライセンスがデジタルライセンスかプロダクトキーかを確認してください。
デジタルライセンスであればMicrosoftアカウントに紐づいているかを確かめてください。
プロダクトキーを使用している場合は、事前にキーをメモしておくと再認証がスムーズになります。
起動メディア作成
WindowsインストールメディアをUSBで作成します。
公式のメディア作成ツールを使えば、最新のWindows11イメージを簡単に用意できます。
作成後はUSBが正しく起動するか、別のPCで一度起動確認しておくと安心です。
UEFI設定
PCを再起動してUEFIセットアップ画面に入り、USBからの起動が優先されるよう設定してください。
Secure BootやCSMなどの設定はマザーボードによって項目名が異なりますので、マニュアルを参照してください。
起動モードをUEFIに統一しておくとGPTでの運用が安定します。
SSD接続確認
初期化前にSSDが物理的に正しく接続されているか確認してください。
外付けケースや直接接続のどちらでも、認識が正常かどうかをOSやUEFIでチェックします。
| 接続方法 | 確認ポイント |
|---|---|
| SATA直結 | ケーブルと電源の接続確認 |
| NVMeスロット | スロットの固定状態確認 |
| 外付けケース | ケースのUSBケーブルと電源供給 |
接続後にディスクが認識されない場合は、別ポートや別ケーブルで再確認してください。
データ消去レベル選択
初期化の目的に応じて消去レベルを選んでください。
単にOSを入れ替えるならパーティション削除と再フォーマットで十分です。
個人情報を完全に消したい場合は上書き消去を行うか、secure eraseやDiskPartのclean allなどを利用してください。
消去レベルが高いほど時間がかかるため、作業時間も考慮して選択してください。
Windowsインストールメディアでの初期化

ここではWindowsインストールメディアを使ってOS入りSSDを初期化し、クリーンインストールする手順を説明します。
事前にバックアップやライセンス確認が済んでいる前提で、具体的な操作と注意点を中心に解説します。
USB起動
作成したインストールUSBから起動するため、まずPCのブート優先順位を確認してください。
電源投入直後に表示されるBIOS/UEFI呼び出しキーを押して、USBを最優先に設定します。
環境によっては一時ブートメニューからUSBを選ぶほうが手早い場合があります。
- F2またはDelでBIOS設定画面
- F12またはEscでブートメニュー
- USBは先頭に配置すること
- セキュアブートは一時的に無効にする場合あり
USBから正常に起動すると、Windowsセットアップの言語選択画面が表示されます。
パーティション削除
セットアップ画面で「カスタム:Windowsのみをインストールする」を選択してください。
ターゲットのSSDを選び、既存パーティションを一つずつ削除して未割り当て領域にします。
複数のパーティションがある場合は、回復領域やEFIパーティションも含めて削除することが一般的です。
注意として、誤ったドライブを削除するとデータが完全に失われますので、表示されている容量やディスク番号をよく確認してください。
ドライブフォーマット
パーティションを削除した後は、未割り当て領域を選んで新規作成することで自動的にフォーマットされます。
必要に応じてNTFSでフォーマットすることが多く、システム領域はセットアップが自動で管理します。
クイックフォーマットと完全フォーマットの選択は環境次第ですが、完全フォーマットは時間がかかります。
セキュリティ面で徹底的に消去したい場合は、フォーマットだけでなくDiskPartのclean allを併用すると安全です。
MBR/GPT選択
UEFI環境ではGPTを、レガシーBIOS環境ではMBRを基本的に選択します。
最近のPCとWindows 10/11はGPTとUEFIの組み合わせを推奨します。
| MBR | GPT |
|---|---|
| レガシーBIOS対応 | UEFI対応 |
| パーティション数制限あり | 多数のパーティション対応 |
| 2TB以上の制限あり | 大容量ドライブ対応 |
変換が必要な場合は、DiskPartでconvert gptまたはconvert mbrを実行して調整してください。
ドライバ読み込み
セットアップがSSDを認識しない場合は、ストレージコントローラのドライバを読み込む必要があります。
ドライバは別のUSBに保存しておき、「ドライバーの読み込み」から指定してください。
特にNVMeやRAIDコントローラは専用ドライバが必要になるケースが多いです。
ドライバのバージョンに注意して、メーカーサイトから最新を用意すると安全です。
再インストール開始
パーティションとフォーマットを確認したら、インストール先を選んで再インストールを開始します。
インストール中は電源を切らないようにして、完了後は初期設定を進めてください。
プロダクトキーの入力はスキップして後から認証することも可能です。
最後にWindows起動後、ドライバやWindows Updateを適用して環境を整えてください。
DiskPartによる完全消去

DiskPartを使うと、コマンドラインからディスクのパーティション情報を完全に削除できます。
手順を間違えると別のドライブを消してしまう危険があるため、慎重に作業してください。
ここでは起動方法からコマンドの意味、注意点まで順を追って解説します。
DiskPart起動
管理者権限のコマンドプロンプトまたはWinREのコマンドプロンプトからDiskPartを起動します。
起動後はまずlist diskなどで対象ディスクを確認する習慣をつけてください。
- Windowsの検索でcmdを管理者として実行
- Windows回復環境からコマンドプロンプト起動
- インストールメディアの修復オプションから起動
list diskコマンド
list diskを実行すると、接続されているディスク一覧が表示されます。
表示されるサイズとディスク番号を照合し、誤ったディスクを操作しないようにしてください。
オフラインや読み取り専用の属性が付与されているディスクもここで判別できます。
select diskコマンド
select disk Xで対象のディスクを選択しますが、Xはlist diskで確認した番号を必ず使ってください。
選択後はdetail diskコマンドでさらに情報を確認すると安全です。
ここで誤ったディスクを選ぶと、以降のcleanやclean allが別のドライブに適用されてしまいます。
cleanコマンド
cleanはディスクのパーティションテーブルとブートレコードを削除しますが、データの中身を上書きしません。
短時間で終わるため、パーティション情報だけをリセットしたい場合に便利です。
ただし、SSD固有の領域に残るメタデータや回収されないデータもあるため、完全消去には向きません。
clean allコマンド
clean allはディスク全体をゼロで上書きするため、ほとんどのデータ復元を困難にします。
しかしSSDに対しては長時間の書き込みが発生し、寿命を縮める可能性があります。
SSDを安全に初期化する場合は、メーカー提供のセキュアイレースやATAコマンドの使用を検討してください。
| 操作 | 効果 | 所要時間 |
|---|---|---|
| clean | パーティション情報の削除 | 短時間 |
| clean all | 全セクタの上書き | 長時間 |
| セキュアイレース | コントローラによる完全消去 | 短〜中時間 |
convert gptコマンド
cleanまたはclean allでディスクを空にした後、convert gptでディスクをGPT形式に変換できます。
UEFIでの起動を行う場合はGPTが推奨されますので、用途に合わせて変換してください。
変換前にディスクが選択されていることを再確認し、必要ならcreate partition primaryでパーティションを作成してください。
操作が完了したらexitでDiskPartを終了し、次のインストール作業に移ることができます。
別PCに接続して行う初期化方法

別のPCにSSDを接続して初期化する方法は、内蔵PCでの作業が難しい場合や、確実にディスクを消去したいときに有効です。
ここでは外付けケースやSATA直結、NVMeアダプタを使う手順と、接続後の認識確認方法をわかりやすく説明します。
外付けケース使用
外付けケースは手軽にSSDをUSB接続にできるため、ノートPCや持ち運び用に便利です。
ケースの選び方や取り付けの注意点を押さえておけば、トラブルを避けつつ安全に初期化できます。
まずは対応するSSD規格を確認してください。
ケースにSSDを取り付ける際は、電源やコネクタの向きに注意して静電気対策も行ってください。
以下は外付けケースを使うメリットと注意点の簡単な一覧です。
- 持ち運びが簡単
- ホットプラグに対応
- USB接続で手軽に初期化可能
- 速度がUSB規格に依存する
- 長時間負荷で発熱しやすい
ケースに接続後は、PCがUSBデバイスとしてディスクを認識するか確認してください。
SATA直結
デスクトップPCにSSDを直接SATAケーブルで接続すると、最大の性能を発揮できます。
接続前にPCの電源を切り、マザーボードのSATAポートと電源コネクタを確実に差し込みます。
接続が完了したらBIOSでディスクを認識しているか確認し、必要に応じてAHCIモードに設定してください。
次に、Windowsや初期化ツールでパーティションを削除してからフォーマットを行います。
以下はSATA直結時のポイント比較表です。
| 項目 | ポイント |
|---|---|
| 接続方法 | SATAケーブルと電源コネクタ |
| 速度 | 最大SATA転送速度 |
| 適した機器 | デスクトップPC |
| 設定 | AHCI推奨 |
作業中は静電気やコネクタの折れを避け、無理に力を入れないでください。
NVMeアダプタ使用
NVMe SSDは接続方法が特殊ですが、NVMe用のUSBアダプタやPCIe変換アダプタを使うことで別PCで初期化できます。
アダプタを選ぶ際は、対応するキータイプと冷却性能を確認してください。
USB接続のアダプタを使う場合、転送速度がUSBインターフェースに制限される点に注意が必要です。
PCIeスロットに挿すタイプのアダプタはより高速ですが、取り付けに慣れが必要です。
アダプタで接続したら、ディスクが認識されるまで数秒待ってから初期化やフォーマットを開始してください。
ディスク認識確認
接続後はまずOS側でディスクが正しく認識されているか確認します。
Windowsではディスクの管理画面を開き、未割り当てのディスクがあるかどうかを確認してください。
認識されない場合はUSBケーブルやSATAケーブルを差し直し、別のポートで再試行します。
それでも認識しないときは、デバイスマネージャーでドライバの有無を確認し、必要であればドライバを更新してください。
ディスクを確認したら、パーティション削除やディスク初期化の方法を選び、目的に応じてMBRかGPTを設定してください。
安全のため、初期化前に重要データが残っていないか最終確認を行ってください。
初期化後に必須の復旧と設定

SSDを初期化した後は、単にOSを入れ直すだけでは終わりません。
安定した動作と長期的な性能確保のために、いくつかの復旧と設定作業を順に行う必要があります。
Windows再インストール
まずはWindowsの再インストールを行います。
インストールメディアを用意し、インストール中に製品キーの入力やエディション選択を行ってください。
必要な場合はパーティションを再作成し、システム用のEFIパーティションと回復パーティションを正しく配置します。
インストール後はWindows Updateを実行して基本的な更新を当て、Microsoftアカウントでのサインインやローカルアカウントの選択を行ってください。
ライセンスの自動認証がうまくいかない場合は、マイクロソフトサポートや購入元に問い合わせることをおすすめします。
ドライバ導入
OSが入ったら、まずはチップセットドライバとストレージドライバを最初に導入します。
その後、グラフィックドライバやネットワークドライバを入れて、基本的な動作環境を整えてください。
ベンダー提供の最新ドライバを優先し、Windows Updateは最後に適用するのが安全です。
- チップセットドライバ
- ストレージコントローラドライバ
- NVMeドライバ
- グラフィックドライバ
- LAN Wi‑Fiドライバ
- オーディオドライバ
- Bluetoothドライバ
ファームウェア更新
SSDとマザーボードのファームウェアは、性能と互換性に直結しますので最新にしておくことが重要です。
更新前には必ずデータのバックアップを取り、電源が安定している状態で作業してください。
メーカー提供のツールを使う方法が最も安全で、手順に従って実行してください。
| 対象 | 推奨手順 |
|---|---|
| SSD | ベンダーツールで適用 |
| マザーボード | UEFIからFlashing |
| NVMeアダプタ | アダプタメーカーの更新ファイル適用 |
TRIM有効化
TRIMが有効であることを確認すると、SSDの長期的な性能維持に役立ちます。
確認方法はコマンドプロンプトで fsutil behavior query DisableDeleteNotify を実行し、結果が 0 なら有効です。
無効の場合は fsutil behavior set DisableDeleteNotify 0 を実行して有効化してください。
さらに、Windowsの「ドライブの最適化」でスケジュールが有効になっているか確認し、自動実行が行われるようにしておくと安心です。
パーティション最適化
パーティション構成はパフォーマンスに影響しますので、用途に合わせて最適化してください。
UEFI+GPT環境ではEFIパーティションを先頭に配置し、アライメントを正しく取ることが重要です。
システムドライブはNTFSを推奨しますが、データ用に別パーティションを切るとバックアップや再インストールが楽になります。
最後に最適化コマンドでトリムと最適化を実行し、アロケーションユニットサイズや空き領域確認を行って完了です。
実行前の最終チェック

必ずバックアップの完了を確認してください。
重要なライセンスやプロダクトキーが手元にあるか、再確認をお願いします。
外付けドライブや別パーティションは切り離し、不要なデバイスは取り外しておくと安全です。
落ち着いて作業してください。
BitLockerや暗号化を一時停止し、UEFI/BIOSの起動順序を確認しておくと安心です。
電源供給やバッテリー残量を確保し、途中で停止しないように準備してください。
対象SSDを間違えないよう、容量やシリアルをメモしてから操作を始めてください。
最後に、作業時間の見積もりを立て、必要なドライバやファームウェアを用意しておくと心強いです。